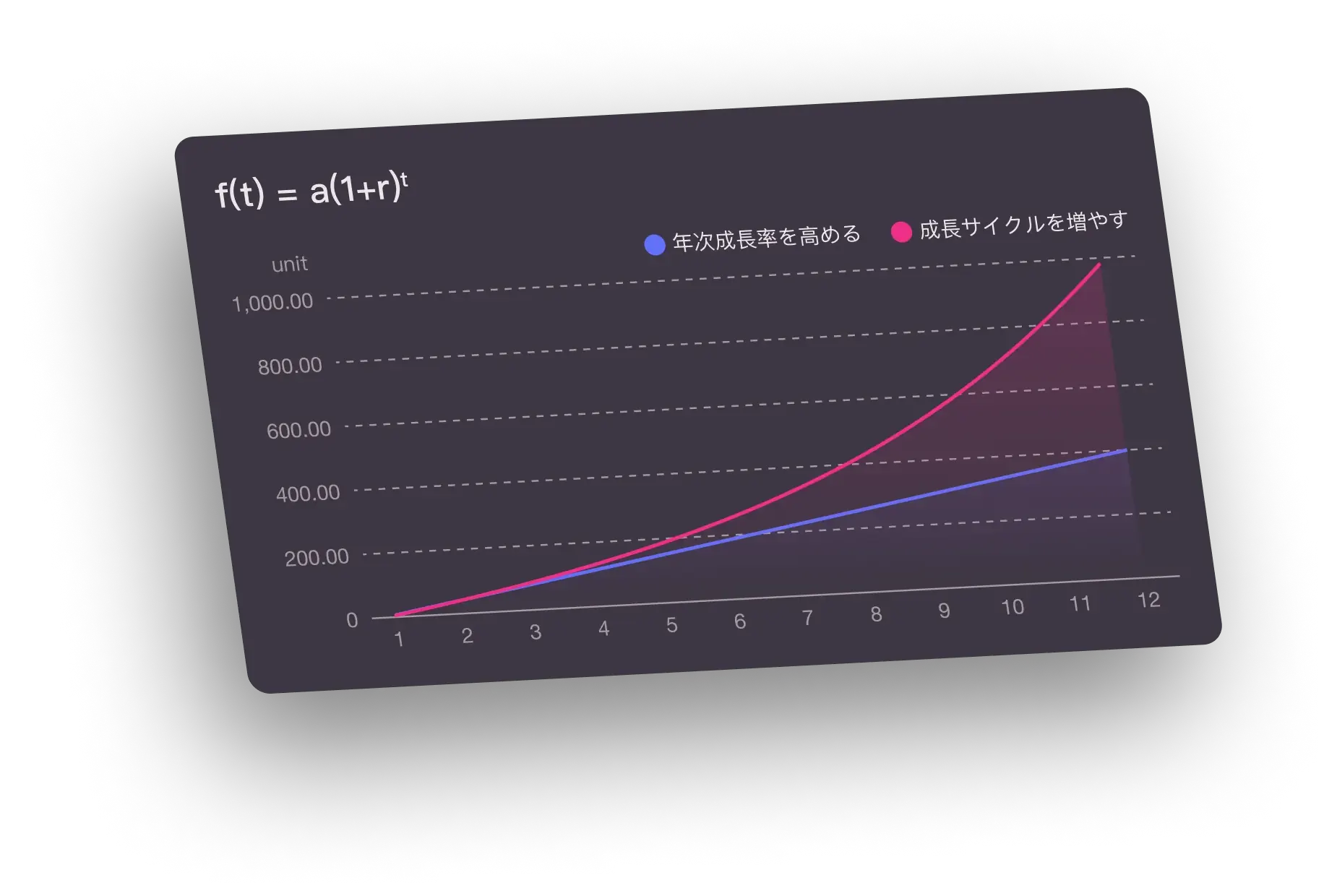「テンプレなんて30分で使えなくなる」
弊社代表、そして『事業計画の極意』の著書である木村義弘がそう断言するのは、何百社もの事業計画を見てきた経験があるからです。木村は長年事業計画に携わる中で、数字が合わない、ストーリーが通らない、チームに浸透しない原因は、ノウハウ不足ではなく「構造の欠如」だと気づきました。
『事業計画の極意』は、そうした現場の課題を解きほぐし、再現性のある計画を描くための一冊となっています。 本記事では、著者インタビューや章別の要約を通じて、『事業計画の極意』をより楽しんでもらえるための情報をお届けします。
1. 『事業計画の極意』の概要

タイトル:事業計画の極意──仮説と検証で描く成長ストーリー
著者:木村義弘(株式会社プロフィナンス代表/グロービス経営大学院准教授)
発行年:2024年
起業家・経営企画・新規事業担当者など、事業計画と日々向き合う人に向けて書かれた実務に効く事業計画ガイドです。テンプレートやフォーマットではなく、「仮説構造」を軸に事業計画を再現性高く作れるようになる点が特徴です。
2. 著者インタビュー
Q1. そもそも、なぜこの本を書こうと思ったのですか?

きっかけは、支援先のスタートアップで事業計画がうまく回っていないのを目にしたことでした。
数字が合わない、ストーリーが通らない、それ以前にチームで共通言語になっていない──そんな場面があまりにも多かったんです。
「これはノウハウの問題じゃない。“考え方”や“構造”の欠如なんだ」と気づきました。 だったら一冊にして、構造ごと体系化しようと思ったんです。
ぶっちゃけ言えば、研修をしていたときに株主さんから「まとめたら?」とか、「本出しなよ」と背中を押され、出版社を紹介されたのが大きなきっかけです。
よくよく振り返れば、自分自身もずっと事業計画で苦労してきました。頼れる本がなく、自分なりに考え抜いたこと、研修で評価をいただいた部分を体系化して残すことは非常に意味があると思ったんです。
Q2. 本書でいちばん伝えたかったことは何ですか?

「良い事業計画って、見た目じゃなくて“良い仮説の構造”だよってこと」
数字の辻褄合わせやテンプレートの完成度ではなく、「なぜこの数字なのか」という因果の構造こそが計画の真髄です。
構造がなければ、計画は前に進むための道具にならない。書いて終わりではなく、次の打ち手を生むための「共通言語」になってこそ意味があります。
実行につながらない計画は、そもそも使える計画じゃない。テンプレなんて30分で使えなくなる。テンプレで出来る事業構造なんて意味がない。だからこそ、僕は「テンプレなんてゴミ箱に捨てろ!」と本気で思っています。
Q3. 執筆中、悩んだことや迷ったことはありましたか?
 正直、一番悩んだのは「どこまで現場っぽく書くか」でした。
正直、一番悩んだのは「どこまで現場っぽく書くか」でした。
専門書に寄せすぎると広く届かない。でも現場で使えるレベルに落とし込むのは本当に難しかった。特にKPIツリーやコストの因果設計は、実務で再現可能な形にするまで何度も何度も書き直しました。
また、当初研修で伝えていたことを文章に落とすと、詰め切れていない部分や曖昧だった点が浮き彫りになりました。書籍を作りあげる過程で自分自身の整理ができてきて、結果研修の質向上にもつながりました。
経験やセンスだけに頼るやり方では、属人化から抜けられません。僕はそれを可視化し、体系化したかった。プロの顔をしている人たちが体系化しなかったから、現場はずっと苦労してきた。だから自分がやるしかないと思ったんです。
Q4. どんな人にこそ、この本を読んでほしいですか?

計画が苦手だと思っている人、特にこれからファイナンスや事業計画に向き合わなければならないタイミングにいる人に、ぜひ読んでほしいです。
数字を作るだけでなく、チームで前に進むための「共通言語」を持ちたい人には、きっと刺さるはずです。
初心者の方にはガイドになり、既に専門家を名乗っている方には棚卸しの機会になります。背景のロジックまで含めて体系化しているので、他の人を指導するときや引き継ぐときにも役立つでしょう。
起業家や経営者は、多くの課題に直面して苛立ちすら感じているはずです。僕もそうでした。だからこそ「もっと早く体系化してほしかった」という想いを爆発させて、本書を産み出しました。ぜひ僕の熱意を受け取っ てください。
3. 章別要約(10分でわかる『事業計画の極意』)
目次の後に章別要約を載せています。
目次
はじめに
Ⅰ 本書の位置づけ
Ⅱ 本書の章立て
第1章 事業計画に向き合う
Ⅰ 事業計画とは
Ⅱ 事業計画の役割
Ⅲ 事業計画不要論
Ⅳ なぜ新規事業・スタートアップの事業計画は達成できない?
Ⅴ いい事業計画とは
補論 事業計画及び成長可能性に関する事項
コラム 「1,000通りシミュレーションしろ」という名経営者
第2章 事業計画にとりかかる前に
Ⅰ 財務諸表を理解しよう
Ⅱ 損益計算書
Ⅲ 貸借対照表
Ⅳ キャッシュ・フロー計算書
Ⅴ 事業計画を作成上必要となる会計の論点
Ⅵ ストーリーで追う数字の動き方
コラム 事業計画は「素振り」
第3章 事業計画全体を設計する
Ⅰ 数字で考える意味
Ⅱ 事業計画では何を作るのか?
Ⅲ 設計思想
Ⅳ 作成する期間の考え方
Ⅴ アウトプットイメージ
Ⅵ 海外スタートアップにおけるフォーマット
Ⅶ どこまで作り込むのか?
補論 表計算ソフトでの表現方法
コラム 事業計画において追求するべき正確さ
第4章 トップラインを考える
Ⅰ 売上を考えるときの視点は?
Ⅱ 売上高の基本構造
Ⅲ 収益構造分解法(KPIツリー構築法)
Ⅳ 収益構造分解の5ステップ
Ⅴ 集客施策の派生形(代理店・取次店)
Ⅵ さまざまな事業の構造化
Ⅶ KPI
Ⅷ 戦略と情熱でトップラインを描く
Ⅸ 表計算ソフトでの表現方法
補論 市場成長の考え方
コラム CFO時代にメンバーに伝えていたこと
第5章 コストは方程式
Ⅰ この事業にかかるコストは何か?
Ⅱ 重要なコストの洗い出し方
Ⅲ 誤解しがちな変動費
Ⅳ 戦略コスト
Ⅴ 戦略コストの方程式化
Ⅵ 変動費の方程式化
Ⅶ その他のコストの方程式化
Ⅷ 費用のトリガー
Ⅸ 表計算ソフトでの表現方法
コラム グローバルデカコーンが見ているたった一つのKPI
第6章 資金について考える
Ⅰ 経営アジェンダにおける資金調達
Ⅱ 資金を考える上での大切なポイント
Ⅲ 資金調達の方法
Ⅳ スタートアップの資金の考え方
Ⅴ エクイティ・ファイナンス
Ⅵ 大手企業における新規事業での資金の考え方
Ⅶ 事業計画の見せ方
Ⅷ 表計算ソフトでの表現方法
第7章 【発展】BS・CFの設計
Ⅰ 最初の鬼門は運転資本
Ⅱ 年払いなどの表現
Ⅲ 設備投資がトリガーとなるビジネス
Ⅳ ソフトウェア開発
Ⅴ 税金
Ⅵ 表計算ソフトでの表現方法
コラム 事業計画と財務モデルの違い
第8章 事業計画を使い倒すPDCA
Ⅰ さあ、素振りをしよう!
Ⅱ PDCAとしての予実管理
Ⅲ 改善の進め方
Ⅳ 意味のあるシナリオ分析
第9章 事業計画で描く経営の未来
Ⅰ 計画を立て、血肉化する
Ⅱ 経営はサイエンスへ
Ⅲ サイエンスこそ、起業家・事業家に必要だ
おわりに
第1章:事業計画に向き合う
事業計画とは単なる“資金調達用の資料”ではなく、戦略を構造化し、意思決定の軸を共有する「経営の思考装置」です。
本章では、事業計画が本来担うべき役割を再定義し「なぜ多くの新規事業の計画は達成されないのか?」という問いに対して、属人性・構造不全・数値未接続といった背景要因を示します。
「良い事業計画」とは精緻な予測ではなく、“チーム全体で仮説を検証できる構造”を持っていること。未来に対して1,000通りのシナリオを描き、変化に応じて柔軟に組み替えられるものこそが、実行可能な計画であると本章では語っています。
第2章:事業計画にとりかかる前に
数字に苦手意識があっても大丈夫。
本章では、事業計画をつくる前提として必要な「財務の基礎知識」を、ビジネスの現場に即したかたちで丁寧に解説します。
P/L(損益計算書)では「売上-費用=利益」の構造を学び、B/S(貸借対照表)では「資産=負債+純資産」のバランスを、C/F(キャッシュフロー計算書)では「実際に動くお金の流れ」を押さえます。
さらに「減価償却」「棚卸資産」「繰延収益」など、事業計画でつまずきやすい会計論点もカバー。数字は、ビジネスのストーリーを裏付ける“もう一つの言語”だという認識が深まります。
第3章:事業計画全体を設計する
いきなり表を埋めるのではなく「どの順序で、どこまで作るか?」をまず考えることが成功の鍵。本章では、トップラインからコスト構造、資金繰りまで、全体をどう設計すべきかという“思考の型”を提示します。
数字で考える意味:数字は検証可能な仮説の器。戦略を実行に移すには「構造」が必要です。
計画の期間:スタートアップなら「ローリングで12〜18カ月先まで」、中長期を見据えるなら「3〜5年分」の設計が一般的です。
精度のレベル:最初から完璧を目指す必要はなく、仮置きでまず描くことが重要。
海外スタートアップのフォーマット:国際投資家向けの「テンプレート的構造」も紹介。
事業計画をExcelやスプレッドシートに落とし込む前に「どんな構造で描くのか」を設計することが、のちの検証・修正・再構築のしやすさを決めます。
第4章:トップラインを考える
「売上=単価 × 数量」という公式に収まらないのが、現代の事業モデル。
本章では、売上構造をKPIレベルで分解し「戦略と現場をつなぐトップライン設計」の重要性を解説します。
特に注目すべきは「収益構造分解法(KPIツリー構築法)」です。顧客獲得、単価設計、利用頻度などをKPIで可視化することで、成果を因数分解し、改善の打ち手を論理的に導き出せるようになります。
また、代理店モデルや取次店など、多様な事業構造の具体例を紹介し、表計算ソフトでの展開方法も掲載。トップラインは戦略の反映であり、情熱をのせた仮説を、ロジックで支えることが必要なのだと伝える章です。
第5章:コストは方程式
コストは、単なる“金額”ではなく“構造”で捉えるもの。本章では、コスト構造の分解と方程式化を通じて、事業の収益性を設計する思考法を紹介します。
固定費・変動費の分類を超えて、コストの「トリガー(引き金)」を特定することで、どの行動がコストを生み出しているのかを可視化できます。さらに、戦略コスト(例:集客のための広告費)を切り出し、意思を持った投資と認識することもポイントです。
誤解されがちな“変動費”の実務的な捉え方や、数式での表現方法も丁寧に整理。最終的には「この事業は、どの入力がどの出力につながっているのか?」という構造的理解へと読者を導きます。
第6章:資金について考える
どれだけ利益が出ていても、キャッシュが尽きれば会社は止まる──本章は、スタートアップ経営における「資金」の考え方にフォーカスします。
資金調達は単なるお金集めではなく、「今の事業フェーズにおいて、なぜこの資金が必要か」を明確に説明する行為です。エクイティファイナンスとデットファイナンスの違いや、調達後のキャッシュフロー設計も解説。
また、大手企業の新規事業では「社内稟議」といった別の文脈で資金が動くため、その違いも補足されます。「事業計画の“見せ方”」についても丁寧に解説しており、投資家や上層部を動かすプレゼンテーションの型もつかめます。
第7章:【発展】B/S・C/Fの設計
P/L(損益計算書)だけでは読み切れないお金の実態に迫るのが、本章のテーマ。
B/S(貸借対照表)やC/F(キャッシュフロー)を正しく設計できるかどうかが、リアルな経営感覚に直結します。
例えば、「年払いの売上」「未収金の発生」「設備投資やソフトウェア開発費」などは、B/S・C/Fでなければ表現できません。また、「運転資本」という初学者がつまずきやすい概念も、ていねいに紐解かれています。
事業計画と財務モデルの違いにも言及し、「未来を描く思考の地図」と「実態に合わせる経営の現場感覚」の両方を行き来する重要性を理解できます。
第8章:事業計画を使い倒すPDCA
「作って終わり」ではなく「使って回す」ことが事業計画の本当の価値。本章では、事業計画を起点としたPDCAの回し方=予実管理の基本を解説します。
・予算と実績のズレをどう捉えるか
・そのズレから、どんなアクションを導き出すか
・意思決定者にとって、どんな粒度での分析が必要か
こうした問いに答えながら、「意味のあるシナリオ分析」や「改善の打ち手の構造化」といった実務に直結する内容を展開。データは責めるためではなく学ぶために使うという哲学が、一貫して流れています。
第9章:事業計画で描く経営の未来
最終章は、本書全体のまとめとして「事業計画とは、未来の経営そのものである」というメッセージを強く打ち出しています。
計画を立てるだけでなく、それを血肉化することで、戦略が日々の意思決定に浸透し、チーム全体がサイエンスと情熱の両輪で動き出します。
「経営はセンスではなくサイエンスだ」「仮説を構造で描き、数字で検証し、感覚を言語化する」。こうした視座を持てるようになることが、起業家・経営者・事業責任者にとって最大の武器になるのです。
4. 著者プロフィール
 木村義弘
木村義弘
株式会社プロフィナンス代表取締役/グロービス経営大学院准教授。
投資家・経営者・支援者の三つの視点を行き来しながら、数百社以上の事業計画に関わる。
自身も「計画が苦手だった」経験を持ち、現場で使える事業計画の体系化に挑んだ。

メーカー営業から出産を経てフリーランスに転身。 ライティング・編集・校正業に携わる。 2025年にマーケ担当としてプロフィナンスにジョイン。